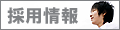セレクト学院では、保護者の方より面談やメール、お電話によってご質問を受けることが多くあります。
この時期は、特に中3生の保護者様からの質問が多く、その一部を紹介したいと思います。
・「私立高校の過去問は買った方がいいか?」
・「公立一本でいきたいが、私立高校は受けないといけないか?」
・「ギリギリで上の高校に入るのと、余裕を持って違う高校に入るのとではどちらがいいか?」
・「うちの子、受かりますか?」
・「私立の推薦を貰えなかった場合は受験はあきらめた方がいいか?」
他にも「願書の書き方や貼る写真について」「個別相談の服装について」などいろいろな質問を受けています。
(なおこれらの質問の中には、どのご家庭から聞かれても同じ回答になるものもあればそうでないものもあるため、ここでは回答を控えさせていただきます。)
受験生の方もそうでない方も、何か気になることがありましたら、どんな些細なことでもお問い合わせ頂きたいと思います。 小林
- 12.20.2023
- Category
当塾生の北辰テスト結果が先日返ってきましたが、ここまで非常に順調に来ています。
特に第1回(4月)の結果と比べると、この半年で大幅に伸ばしている人も多くうれしい限りです。
ただ個々に見ていくと、それぞれウイークポイントがあったりもったいないミスをしていたりする生徒も見受けられます。今後改善していくことによって更に伸ばして行くことができますので、引き続き向上心を持って取り組んで行ってほしいと思います。
さて、次回の北辰テストですが、実質私立高校の推薦対象の最後のテストとなります。すでに推薦を貰っている人も、今度の成績次第で1ランク上の学科での推薦を貰えるかもしれません。また公立高校受検者にとっても、志望校を選択する際に大きな目安となっていくことと思います。そういう意味でも、非常に多いな意味を持つテストと言えます。
今回の北辰テスト対策は、通常よりも日数を増やしています。「予想模試」と「解説授業」によって、実力を伸ばして行きましょう。 小林
- 11.23.2023
- Category
10/28(土)は北辰対策授業がありますので忘れずに時間通りに集まりましょう(クラスにより時間帯は異なります)。
北辰テストが終われば中3生はすぐに学校の期末テストが迫ってきます。テスト勉強が続き大変ですが体調に気をつけて頑張っていきましょう。
セレクト学院 中村
- 10.26.2023
- Category
セレクト学院では、授業中はもちろんのこと自習時間でも自由にいつでも質問をすることができます。質問の教科は塾で習っていないものでも可能です。そして、出来る限り迅速に対応していますので、きっとその場で満足してもらえるはずです。
また、自習時には塾の先生から質問がないかどうかを尋ねることもあります。
さて、質問の内容にもいろいろとあります。中には「この単語のスペルが分からない。」といったものもあります。これは、実際には自分で調べればわかることなので、私どもは「これは自分で調べてみようね(但し自分で調べる方法が分からない場合は一緒に指導をしていきます)」と言います。
また数学の計算問題のような場合には、極力ストレートに教えるのではなく、数字を変えて類題を作りやり方を教えて行きます。そうして行かないと、質問した問題が学校の宿題で、結局は塾の先生が代わりにやってしまったとなりかねないからです。
このように、質問に対して直接答えていないことも多々ありますが、こういったことを繰り返すことによって「どのようなときに質問をすればいいのか」ということも生徒たちは分かってくるものです。
また質問というのは、ある程度分かっていないとなかなかできないものです。例えばスペイン語やポルトガル語などを1時間教わって、その後に「質問はあるか?」と訊かれてもほとんどの人は何も質問をしないでしょう。分からない所だらけだと、分かろうとする意欲もなくなり、また何をどうやって訊けばいいのかさえ分からなくなってきます。
つまり質問をしてくる生徒よりも、全くしない生徒の方が危険な状況である可能性がはるかに多いのです。そういった点も熟知した上で毎日の指導にあたっています。 小林
- 10.13.2023
- Category
今回は勉強のやり方について1つだけ(でもこの1つがとても重要)お話をしてみたいと思います。
例えば、英語のテストや授業等で「October(10月)」が出題されて、それが書けなかったとします。
そのようなときに、どのような勉強をしていくかでこれからが大きく変わっていくと言っても過言ではありません。
①全く気にならず放置してしまう。
②とりあえず、Octoberが正解だということを確認する(確認をするだけ)。
③Octoberを書けるようになるまで練習をする。
④1~12月までを全てかけるかどうかを確認する。
もちろん④のように学習をしていくのが正しいやり方と言えます。「月」と「曜日」のような基本が1つでもできていなかった場合には、他も不安になって確かめてみる必要があります。こういった勉強の積み重ねで、実力がついていくのです。
当塾にも、まだ①や②のレベルである生徒もいます。しかし、じっくりと先生が向き合って、成長させていけるように指導しています。
また、英語以外でも同様です。例えば社会科(地理)で「筑紫平野」が書けなかったら、日本の有名な平野の名前と場所をチェックしておくこと、数学の「確率」の問題ができていなかったら類題を見つけて何題も解いてみること、こういった積み重ねが大事なのです。 小林
- 10.12.2023
- Category

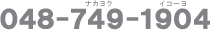

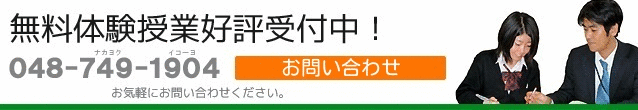
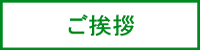

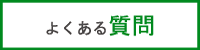
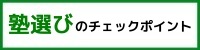
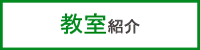

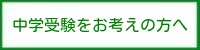
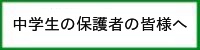
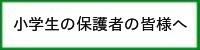
 RSS1.0
RSS1.0